|
|
|
|
|
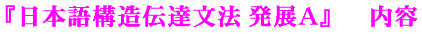 |
|
|
|
|
|
|
|
◆A 部 「格」について 部 「格」について |
|
|
|
A1章 |
主格を3基本主格と12機能主格に分類し,主格のすべての形式が把握できるようになった。 |
|
|
|
A2章 |
「を」が何であるのかは歴史的な形成過程をみれば理解できることが分かった。 |
|
|
|
|
|
|
|
◆A 部 「テ,タ」について 部 「テ,タ」について |
|
|
|
A3章 |
動詞テ形音便が一つの規則の下に説明できるようになった。 |
|
|
|
A4章 |
動詞タ形の示すアスペクトを「局面変化完了認知(開始・区切り・完了)」の側面からとらえ,これを図示した。また,テの示すアスペクト領域の歴史的変化について考察した。 |
|
|
|
|
|
|
|
◆A 部 「条件表現」について 部 「条件表現」について |
|
|
|
A5章 |
出来事生起の確実性を水域(時空モデル)上で示せるようになった。 |
|
|
|
A6章 |
「バ」の構造を図示し,仮定・確定等の領域を水域上に示した。 |
|
|
|
A7章 |
「条件」が,出来事の舟の確定水域への移動という形でモデル化できた。 |
|
|
|
A8章 |
「タラ」の構造を図示し,「バ」との関連を示した。「バ・タラ」の使用を4要素で特定することを示し,今後の調査・考察の方法とすることにした。 |
|
|
|
|
|
|
|
◆A 部 「まえ・あと・とき」について 部 「まえ・あと・とき」について |
|
|
|
A9章 |
絶対テンスと相対テンスの関係が図示できるようになった。 |
|
|
|
A10章 |
(まえ・あと・とき使用)複文での絶対テンスと相対テンスの関わりを場合別に検討した。 |
|
|
|
A11章 |
「とき」を修飾する従文が絶対テンスもとれることについて考察した。 |
|
|
|
|
|
|
|
◆A 部 「従文のテンスとアスペクト」について 部 「従文のテンスとアスペクト」について |
|
|
|
A12章 |
従文を,絶対テンスによる従文,相対テンスによる従文,質としての従文に分類した。 |
|
|
|
A13章 |
従文を絶対テンス・相対テンスでとらえる場合のすべてを図記号で示し,体系的な一覧表にした。 |
|
|
|
A14章 |
従文内容を質的にとらえる場合を図示した。 |
|
|
|
A15章 |
従文が形容詞文である場合の絶対・相対テンスのあり方を,図記号を用いて一覧表に示した。イ形とタ形の使い分けと誤用について考察した。 |
|
|
|
|
|
|
|
◆A 部 「実体修飾法」について 部 「実体修飾法」について |
|
|
|
A16章 |
第1修飾法(いわゆる連体形による修飾法)による修飾の,ありうる構造関係を分類整理した。諸用語を定義して,自属性による修飾の構造,他属性による修飾の構造,包含実体の修飾される構造について考えた。また,基準点と関係のある修飾についても考察した。 |
|
|
|
|
|
|
|
◆A 部 「諸題」では 部 「諸題」では |
|
|
|
A17章 |
構造を形成する力として「構造形成6力」及び慣用力に基づく「基形成7力」があることが判明した。 |
|
|
|
A18章 |
多義文を生成する構造を何種類か示した。 |
|
|
|
A19章 |
「ようだ・みたいだ・だけしか」などの構造を示した。 |
|
|
|
|
|
|
|
◆A 部 「構造練習帳」では 部 「構造練習帳」では |
|
|
|
[1]〜[30] |
『文法』の範囲内にある構造の読み描きが練習できるように,構造図を集め,チェックリストをつけた。立体図と,対応する平面線画が示してあるので,すべて平面線画で練習することも可能である。 |
|
|
|
|
|
|
