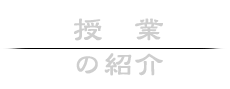
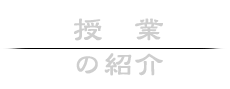 |
| <原田範行研究室紹介TOP> <主要研究分野の紹介> <授業の紹介> <原田ゼミナ−ル(卒業論文演習)の紹介 > |
| 私の専門分野についての講義科目の一つに「英米文学特論」という授業があります。この講座については、いつも、次のような私の文章を、そのイントロダクションとして学生の皆さんに読んでもらっています。ここではそれを紹介することで、私の授業や研究分野の面 白さの一端を味わっていただきましょう。 |
「Johann Sebastian Bach は、"Bach" (=小川) でなく、"Meer" (=大海)である」とは、ベ−ト−ヴェンの洒落であるが、それ以前の音楽の伝統を吸収し、それ以後、現代に至る音楽史に決定的な影響を与えた点で、バッハの偉業は、単なる洒落以上に、確かに"Meer" と考えられても不思議ではない。実は、バッハが生まれた1685年あたりを嚆矢とし、その後、啓蒙の時代と呼ばれる18世紀のヨ−ロッパには、音楽だけでなく、学問・芸術・政治の面 で、このような傑出した人物や業績が数多く見いだされる。例えば、同じドイツでは、やや遅れてカントやゲ−テがいる。フランスでは、ヴォルテ−ルやルソ−がいる。『百科全書』がパリで刊行されたのは、バッハがこの世を去った翌年の1751年のことであった。ヴァイオリン製作者ストラディヴァ−リや歴史主義哲学者ヴィコがイタリアで活躍したのも、ほぼこの時代に属する。(一方、日本では、やや早く、関孝和や井原西鶴、近松門左衛門が登場し、また18世紀後半には、杉田玄白や平賀源内がそれぞれ独自の業績を残している。) バッハと同い年のヘンデルが、「水上の音楽」を発表し、その生涯の三分の二を過ごしたイギリスの場合も同様である。ただ、この国の18世紀が、他の諸国と決定的に異なるのは、一人の文化的巨人や名君の存在が際立つというよりも、むしろ個人の自由な活動によって生み出された業績が集合体をなし、それが、社会に内在する習慣もしくは制度として、広く浸透し定着していったということであろう。実際、ヘンデルがテムズ河畔で、かの「水上の音楽」を献じたジョ−ジ1世は、今世紀まで続くハノ−ヴァ−朝の開祖ではあるが、ほとんど英語を解さなかった。彼がイギリスの王位 に就いた1714年には、フランスにルイ14世、プロイセンにフリ−ドリッヒ=ヴィルヘルム1世、ロシアにピョ−トル1世といった専制君主が存在したが、これに対するジョ−ジ1世の存在感はきわめて希薄である。ト−リ−・ホイッグ両党による議会政治がいち早く機能し始めたのは、こうした事情によるところが少なくない。また、今日、我が国の憲法でもうたわれている「言論の自由」という理念は、詩人ミルトンが、既に1644年に発行した政治パンフレット「アレオパジティカ」において提唱したものだが、これが、出版物事前許可制法の失効という形で具体化したのは、実は、その半世紀後のことで、ミルトンの高邁な思想とは別 に、貿易上の不利益というきわめて現実的な理由によるものであった。(興味深いのは、出版の自由という理想を大衆的な経済問題にすりかえることを国会議員に入れ知恵したのは、哲学者ロックである。)ほぼ18世紀いっぱいを生き抜き、今日、「国民的名物男」の名をほしいままにするジョンソン博士は、なるほど浩瀚な『英語辞典』をほとんど独力で編纂した傑物だが、その性格は、ルソ−やカントの場合とは明らかに異なる。彼は各個人の理性を重視し、一義的な判断や画一的な行動を極度に嫌った。『英語辞典』の作成をはじめ、『シェイクスピア全集』や『詩人伝』の編纂、定期刊行物や小説、詩の執筆など、彼は幾多の業績を残しているが、結局のところそれらは、異なる二つ以上の見解を併記し、最終的な判断を読者に委ねるという特質を内包していたのである。 イギリスの近代は、概ね、このような状況のもとに形成され推移していく。この国の「啓蒙時代」に生み出されたものの多くが、19世紀以降の世界に大きな影響力を持ちえたとすれば、それは、イギリス18世紀文化が持つ、ある種の匿名性によるところが少なくない。主としてイギリス近代の文化と文学を講ずる本講座は、こうした歴史認識を基に、具体的なテクストに言及しながら、定期刊行物(ジャ−ナリズム)の勃興、韻文の持つ文化的社会的性格の変化、散文精神の成熟と小説 (novel)の発生、演劇と劇場の変容、そして最終的には、文学 (literature) という概念そのものの変化を考察していくものである。本稿では、これらの各論を集約しつつ、講義のねらいを明らかにすることにしたい。 ところで、外国語学部の学生諸君が、卒業に際して授与される学士号のことを、正式には「文学士」と言う。外国語学部だけではなく、例えば、自然科学に近い実験心理学や、数学に近い論理学を専攻した文学部学生の場合も、通 常は、卒業と共に「文学士」となる。そこで、「自分は文学をやったわけではないのに」と不思議に思う学生が出てくることになるわけだが、学士号や博士号の単なる名称の問題以上に、「文学」という言葉の意味内容について、ここに注目すべき重要な問題が隠されている。もともと「文学」という言葉は、孔子が、10人の弟子の才能を、徳行・言語・政事・文学に分けた『論語』の「先進篇」に見い出されるものである。(「言語」というと、本学部に最もふさわしいようだが、これは、「弁論の術」の意で、むしろ今日の「広報渉外活動」といった意味に近い。)文学の才があるとされた子游と子夏の行動を追うと、この「文学」という語の指す意味は、概ね、文化の根源たる美、もしくは、今日言うところの文化全般 を愛する心といったことになる。この考え方からすれば、外国語学部を卒業した学生諸君が文学士であってもおかしくはない。少なくとも、現在私たちが、「文学青年」などという言葉で一般 に連想する「文学」は、「狭義の」という注釈付きでなければならないことになる。同じことは、「文学」という訳語を与えられた "literature" についても言える。この "literature" の語源の一つであるラテン語の "litteratura" は、もともと「書きもの」という意味であった。紙そのものが貴重品であった時代、「ものを書いて残す」ということは、それだけで一つの文化であり、また学問的見識の必要とされる事柄なのであった。(現在でも、口語表現として、"printed matter of any kind" という意味がある。)この観点からすれば、ちょうど『論語』に現れる「文学」と同様、今日の大学の、特に人文・社会科学系の学部や大学院で行われている研究活動の多くに、文化や学問全体を総称する「広義の」"literature" という言葉をあてはめることは、あながち不可能なことではない。もしそうした呼称が、奇妙に感じられるとすれば、それは、どこかで、この "literature" (あるいは「文学」)の語義が、否、文化や学問の形態そのものが、大きな変化を遂げたからにほかならない。実は、この質的変化をじっくりと観察できる時代こそ、今からおよそ二百年ほど前の、18世紀イギリスなのである。というのも、啓蒙専制君主や文化的巨人が不在であったがゆえに、当時のイギリスの文化の変容は我々にとってもきわめて身近であり、かつ普遍的な広がりを持つに至ったと考えられるからである。 それでは、この質的変化とは、どのような形で起きたのか。極言するならば、人々が持つ世界観と社会の秩序に対する認識の趨勢が、根本的に変わったということである。神と人間とその他の生物を結ぶ偉大な存在の連鎖(the great chain of being)に対する意識が弱まり、一個の人間が一個の人間として自立し始めたということである。むろん、「来世信仰」のようなものは、日本人だけでなくイギリス人にもある。「輪廻転生」といった意味内容を表す "metempsychosis" といった英単語も、決して死語ではない。けれども、そうした容易には判断の下せない問題をひとまず棚上げし、現実に今を生きる人間に、しかも封建的な一人の権力者にではなく、所詮は心臓というポンプによって動かされているにすぎない一人一人の人間一般 に、世界観の主体を移動させたということである。(ウィリアム・ハ−ヴェイが、人体解剖によって血液循環と心臓のしくみを明らかにしたのが17世紀前半、球体をした地球上のあらゆる物質が、どうして奈落の底に落ちないのかを解明したニュ−トンの万有引力の法則の発見が17世紀後半、「時間とは一人一人の人間が認知するもの」として、「神が先か、時間が先か」といった論争を棚上げしたロックが活躍したのが17世紀後半から18世紀初頭、いずれもケンブリッジやオクスフォ−ドを巣立ったこれらのイギリス人の理論が、18世紀全般 を通じて徐々に一般社会へ浸透していくのである。)人物の足跡を記録する伝記が、国家や宗教との直接的なつながりをもって語られる聖者伝や年代記の段階から、興味深い「個人の歴史」そのものを対象とする本格的な "biography" に変わっていくのもまた、きわめて自然な成り行きなのであった。(ちなみに、"biography" という英単語が登場するのは、1683年頃のことである。) 政治制度を含む広汎な文化の主体が、ほかならぬ 自分自身を含めた一個人であるということに一人一人の人間(といっても、この範囲が、いわゆる下層労働者や奴隷層にまで及ぶのは19世紀以降のことだが)が自信を深めたとき、彼らが求めたものは、多くの情報を得るということと、自分の意見なり創造世界を世に問うということであった。必然的に、複雑な約束事を前提とする "poetic diction" に代わって、平易な散文 (prose)が文化の中心に位置づけられてくる。17世紀、革命と政治的動乱の中で生まれた政治パンフレットは、18世紀に入ると、多様な情報を盛り込んだ定期刊行物 (periodicals) へと変貌する。それまで、一般庶民の話題ではなかった学問的・文化的・政治的議論が、例えば、アディソン、スティ−ルの『タトラ−』や『スペクテイタ−』、あるいはケイヴの『ジェントルマンズ・マガジン』といった定期刊行物を通 じて、散文という一般的な情報媒体の中に吸い込まれていくのである。(商品の貯蔵庫という意味の "magazine" が、「情報の貯蔵庫」として雑誌そのものを意味するようになるのは、この『ジェントルマンズ・マガジン』以降のことである。) 情報媒体としての定期刊行物の隆盛は、自ずと、そうした媒体を利用する読者層を拡大していく。18世紀初頭には、20%程度であった識字率 (literarcy)は、一世紀後には、80%近くにまで上昇する。文字情報を読むことで各個人が人生を考え、また自ら文字情報を発信して意見を世に問うことで、自己の理念を実現に近づけていく…こうした文化のあり方が急速に定着してくるのである。文学史上、近代小説のはじまりとされるリチャ−ドソンの『パメラ』(1740)が誕生する素地は、こうして作られていった。(もっとも、今日、『世界文学全集』といったアンソロジ−には必ず顔を出す、デフォ−の『ロビンソン・クル−ソ−』(1719)やスウィフトの『ガリヴァ−旅行記』(1726)といった作品は、『パメラ』の刊行よりも早い。近代小説特有の "interest in human relationship" に欠けるところが多いため、これらを「小説」の範疇に入れないことが一般 的ではあるが、こういった冒険譚の読者が、後の小説の読者として成熟していったことは間違いない。) 出版形態(というよりも情報の発信形態そのもの)もまた、自ずと、変化せざるをえない。発信した情報が流通 すること、そして流通することで、出版が一つの経済行為として成り立つこと、こうした問題が文化に占める比重はにわかに高まり、それまで、何らかの形で、学問や文化の発信に関わってきた王侯貴族などのパトロンの勢威は、急速に弱まってくる。「かつて御玄関脇に伺候致候ひしより、否御玄関先にて拒絶の命に接し候ひしより、はや七年を経過致候(中略)今日まで自力にて事業を継続つかまつり候以上は、この後はなおなお他人の恩は蒙るまじき考に候」(夏目漱石『文学評論』中の訳文)とは、かの『英語辞典』完成直前になって援助を申し出たチェスタ−フィ−ルド伯爵に対して、ジョンソンが送った書簡の一節である。文学作品の執筆がパトロンから独立する象徴的な出来事としてあまりにも有名であるが、このことは同時に、ほとんど三文文士に近かった当時のジョンソンですら、その才覚によって、巨大な『英語辞典』を出版することが可能であったということを意味している。後にジョンソンは、国王ジョ−ジ三世より『詩人伝』編纂の命を受けるが、彼はこれにも即座に応じはしない。実際に彼が『詩人伝』の編纂に取りかかるのは、それから約10年後、ロンドンの書店組合からの敬意を込めた要請を受けてからのことである。イギリスの「啓蒙時代」が、あくまでも、中央集権的な文化とは対極にあったことを示す好箇の事例である。 こうして見てくると、今日、我々が当然のことと見なしている文化や社会の形態が、実は18世紀のイギリスあたりで、ようやくその目鼻だちがはっきりしてきたものにすぎないということが分かる。匿名性を帯びた大衆が、さまざまな文化的事象の表舞台に、その巨大な姿を現してきたのである。しかしながら、ここで考えなければならないことは、そうした過程で、当然、失われたものが存在するということである。学問と芸術と現実の政治が密接に結びついて一つの有機体を構成し、かつての「書きもの」を大事に育てていた小さな集団は、「前時代的」なものとして、文化の民主的大衆的性格の前に膝を屈し、一方、"literature" は、そうした時代変化の中にあって、なんとかこの大衆との共存の道を模索すべく、限られた文学作品を指し示す言葉として、その意味内容の幅を狭めていく。今日、「文学 (literature) 」という語をもって連想される事柄の多くは、この狭められた意味にほかならない。だが、もし我々が、没個性的な現代社会に対して、ある種の不満や閉塞感を感じるとするならば、それは、まさにこの民主的大衆的性格によって失われた文化の包括的有機体的特質への憧憬の表れであるとは言えまいか。むろん歴史は後戻りしない。語義を狭めた「文学 (literature) 」が、その意味内容を復元することを望むわけでもない。重要なのは、両者の本質を等分に見極め、新たな文化の形態を模索することにある。本講座の最終的な目標は、学生諸君に、こうした推移の諸相を出来るかぎり立体的・具体的に提示することで、現代社会と文化の出発点を確認してもらい、来るべき21世紀の文化の方向性に関する指針を自ら検討してもらうことにある。 |