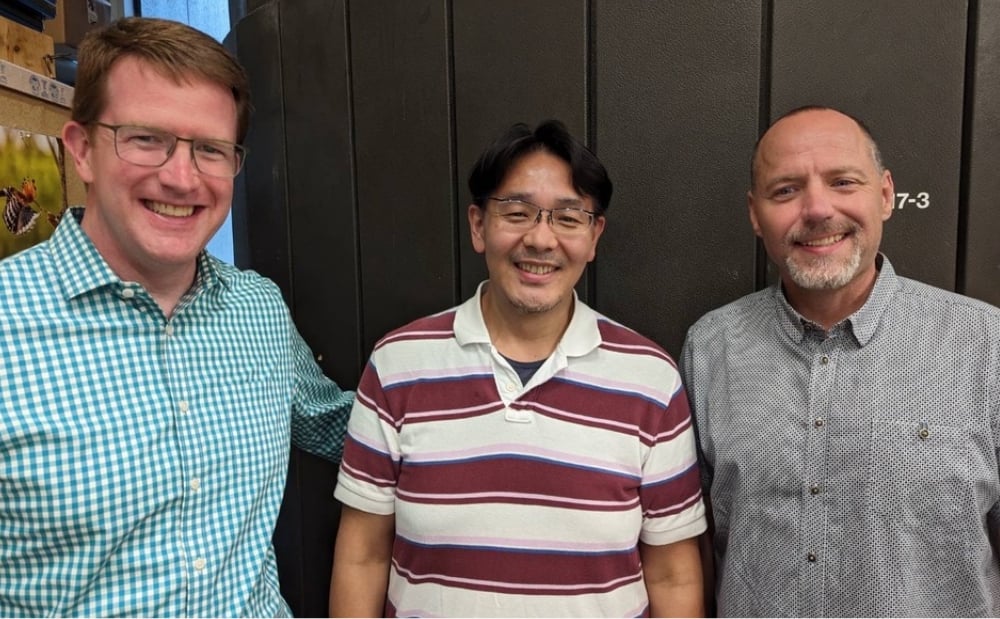さまざまな専門家の意見や実験技術にアクセスしやすい
留学をしようと思った理由を教えてください。
- 自分が所属する科に留学するのが一般的だと考えられていますが、私はこれまで「重症病態下の末梢循環生理」を研究しており、国立保健医療科学院の牛山明先生との共同基礎研究において発展研究の必要性があると感じたため、Massachusetts General Hospital(MGH)のRadiation Oncologyに留学することにいたしました。MGHのRadiation Oncology にはEdwin L. Steele Laboratoriesがあり、癌微小循環の最先端研究を行なっているため、ここを留学先に決めました。また留学を決めたもう一つの理由として、誰にも知られていない場所で、研究者としての自分を試したいという気持ちもありました。
留学先ではどんな風に過ごされていましたか?
- 8時半~9時ごろに出勤して、20時前後に帰宅しておりました。動物や細胞を使った実験をするほか、週に3回行われる勉強会やLab meetingに参加。土日も必要な実験があれば出勤していましたが、週に1日は完全に休養日をつくるようにしていました。家族とBoston観光に出掛けたり、一人でBoston市内を自転車で散策したりして過ごしていました。

留学先で感じたことや得られたことについて教えてください。
- 研究に関して言えば、「癌微小循環環境や癌転移に関するグリコカリックスの役割の解明」というオリジナル研究を立ち上げるなど、異なった専門知識を持った多くの研究者から助言をもらいながら発展的な研究ができたことは非常に価値があることでした。円安とインフレの影響を受けて、金銭的には苦しい日々でしたが、同じような境遇の日本人研究者と助け合い、苦しみと喜びを分かち合いながら過ごす中で一生の友人ができました。また、ハングリー精神を養うことができて、仕事に対する考え方は変わりました。日本の病院とMGHと相違点は、日本に比べて、スタッフが自分の勤務している病院に対して誇りを持って働いていたことです。
経済的な課題はあるものの、留学するメリットはある
留学するにあたり奨学金制度などは利用されましたか?
- 杏林大学の留学制度を利用して、奨学寄付金を支給していただきました。その他にも、企業との共同研究としての研究資金提供があり、MGHでの基礎研究費として一部使用いたしました。これから留学しようと考えている人は、可能な限り奨学金の申請を早めに行った方が良いと思います。特に現在のような円安の状況であれば、留学先の条件がドル建てで記載されている場合、選択可能なら奨学金もドル建てで支給してもらうことをおすすめします。
ご自身の経験を踏まえて、留学を考えている方にアドバイスはありますか?
- 留学前の準備としては、やはり英語力をできるだけ身につけておくほうが良いです。私自身、もう少し日本でやっておくべきだったと後悔しました。
留学先でのモチベーション維持に関しては、限られた留学期間で何ができるか、自分は何のためにここに来たのかを常に自問自答していました。研究者同士で飲むビールや共有した時間はモチベーションの維持に役立ちました。自分から見ると、非常に優秀に思える人も、意外と自分と同じ悩みを抱えているものです。
最後にメッセージをお願いします。
- 世界情勢を勘案すると、日本人が今留学することは経済的にかなり不利です。しかし、自分のしたい研究や行きたい研究室があれば、多少の犠牲を払っても海外で自分を試すべきだと思います。日本から外に出てみないと気づけないことがたくさんあります。できるだけ日本でさまざまな研究費を獲得しつつ、留学先と給与面のタイトな交渉もするべきです。日本人は明らかに遠慮しすぎで、他国の研究者たちは必ずやっています。自分に本当の意味で能力があれば、留学先が経済的な支援をしてくれます。
最後になりましたが、この記事が一人でも多く留学を考える研究者にとって、研究留学を実現できる一助になれば幸いでございます。