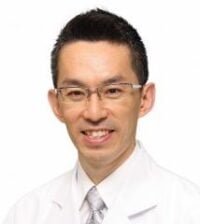よりクオリティの高い研究ができる環境を求めて
早速ですが、福井先生が留学をしようと思ったきっかけはあるのでしょうか?
- 杏林に移ってくる前は聖路加国際病院で臨床を軸にやっていたのですが、膠原病を学ぶ中で研究もできるようになりたいと思うようになり、聖路加国際大学公衆衛生大学院で臨床研究を始めました。やり始めると楽しくて、どうせならトップレベルの場所で臨床研究を突き詰めたいと考えて、留学することを決めました。Brigham and Women's病院のRheumatologyにはSection of Clinical Sciencesという部署があり、臨床研究だけで50名以上が在籍していて、アメリカでも一二を争う膠原病の臨床研究組織があります。

臨床研究は膠原病だけに限らず、多種多様なフィールドで行っているのでしょうか?
- 部署としては、医師主導の治験や保険データベースを扱う研究のほか、基礎研究部門もあるので免疫学やバイオインフォマティクスも扱っています。私は主に関節リウマチ患者さんのレジストリデータやいわゆるビッグデータを使ったデータサイエンスを行っています。
そうすると疫学や統計学など、今まで医師が苦手としてきた領域の知識も必要になりそうですね。聖路加国際大学公衆衛生大学院で学ばれたことは生かされているのでしょうか?
- そうですね。私は2年間、聖路加国際大学公衆衛生大学院で疫学・統計学については学んでから留学したので生かされているとは思います。ただ修士課程でできることはそこまでレベルが高くないので、自分でいろいろ勉強してきました。そこが今とつながって、こちらのスペシャリストと話す中で、疫学や統計学の知識とスキルが少しずつ上がっているのは実感します。もし何も準備していない状態でこちらに来ていたら、今以上にかなり困っていただろうと思います。
英語はどのくらい勉強してから留学されたのですか。
- 特別な準備はしませんでした。聖路加にいるときに膠原病科のカンファレンスなどはすべて英語でやっていて、基本的には英語で会話するのが当たり前の環境だったので、それに助けられています。ただもっと準備しておくべきだったと感じています。
福井先生は今回の留学にあたり、杏林大学の制度を使われていると伺っていますが、大学のサポートについてどう感じていますか?
- まずお伝えしたいことは、私にとって非常にありがたい制度で、とても助かっているということです。私は博士号を持たずに留学しているのですが、修士号だけだと申請できる奨学金の応募先や種類が非常に限られます。今回は幸い杏林大学の制度を使わせていただくことができました。救急総合診療科の長谷川教授、松田理事長をはじめ、サポートを頂いている皆様に心から感謝しております。私のように、いわゆる王道のキャリアではない人にとっても留学の道がひらけるところが、とてもありがたいと思います。
日本ではできない経験が豊かさにつながる
学生時代にも留学をされたことはあるのでしょうか?
- 私は名古屋市立大学出身なのですが、6年生のときにオーストラリアとアメリカに留学したことがあります。国によって医療制度や雰囲気が違っているので、その場所に行って、さまざまなものに触れることの面白さは学生時代に感じていました。あの経験は、今回の留学にもつながっていると思います。
学生時代に海外を経験しておくことは視野を広げるという意味でも役に立つし、その先のモチベーションにもなるということですね。
- 杏林大学には学生の留学を支援する制度があると伺っているので、もし留学するか悩まれている学生さんがこの記事を読んでいるとしたら、ぜひトライしてもらいたいです。
では、次に現在の留学先での生活について伺わせてください。まずは仕事面についてはいかがでしょうか?
- スペシャリストが多いという点は、日本との大きな違いです。臨床研究で疫学・統計学を専門にしている方はなかなか日本にはいないのですが、アメリカには膠原病領域を専門とする生物統計家 (biostatistician)や疫学者 (epidemiologist)と呼ばれる方がいます。自身のプロジェクトについてディスカッションする際に、プロの生物統計家や疫学者から専門的なコメントをもらえる経験は、日本では絶対にできないと思います。ハーバードの研究のクオリティマネジメントは優れているとわかりました。例えば、学会にアブストラクトを提出する際には、共著者だけでなく、部署全体のファカルティーが一斉にアブストラクトを読んで、たくさんのコメントを返してくれます。自身や共著者にはなかった視点を提供してくれるコメントも多く、研究のクオリティの改善に寄与していると感じました。
私生活についても、どんな風に過ごされているか教えていただけますか?
- 日本との文化の違いがあって、こちらでは家族を非常に大事にしたうえで仕事をしていると感じます。朝6時から病院にいる代わりに、17時には基本的にみんな家に帰って子どもと遊ぶなど、家族の時間を大事にしています。私も日本にいるときより家族と過ごす時間は増えました。実はこちらで子どもが生まれて、子育ての大変な時期に妻といっしょに子どもに向き合えていることは、自分にとって大きな財産になっています。研修医として働き始めてから、時間がなく料理をしなくなっていたのですが、こちらに来て料理を再開しました。物価高や円安の影響で、外食がなかなかできなくなってしまったことも一つの理由ですが。
お話を伺っていると、私もシカゴにいたときのことを思い出して、いろいろお話したいところですが、最後に学生さんや若い先生たちにメッセージをお願いします。
- シンプルに考えることが大切だと思います。留学のハードルは確かにありますが、留学したほうが人生にとってエキサイティングな経験ができて楽しいと私は思います。もちろん興味がない人が無理にする必要はありませんが、留学を迷っているような方は、留学したほうが悔いもなく楽しいのではないでしょうか?
研究面では、大きなプロジェクトに関われて刺激がありますし、私もなんとか膠原病領域のトップジャーナルに論文を掲載することができました。
家族との時間も日本に比べると確保しやすいと思います。また、少し時間に余裕が生まれることで、自分が今後どのように仕事や家族、趣味などと向き合っていきたいか考える時間もできます。
経済的にはシビアな面があり、準備は必要ですが、杏林の素晴らしい制度もありますので、こちらを活用してぜひ留学されることを強くおすすめします。

※本記事は2024年7月にオンライン会議システムを使用して、日本にいる田中先生がBrigham and Women's Hospitalに留学中の福井先生にインタビューした内容をもとに作成しています。