病院・診療科について『親と子のケアをもっとよくする会』が開催されました
作成日時 2012年06月04日
スズキ記念病院は宮城県岩沼市にある産婦人科専門病院で、昨年3月に起きた東日本大震災で大きな被害を受け、ライフライン等が寸断された中でも1日も休まず診療を続けた病院です。八木橋先生は実際の災害時に母子への医療の最前線でご活躍され、震災以降は災害支援に関する講演を数多く行っています。
今回のテーマは、今後首都直下型地震の発生確率が3年以内に70%と言われているなか、母子を支える私たち助産師・看護師がこうした災害にどのように備え、どう支援していくかを学び、災害看護の視点と対策の知識を深めていく必要性を感じてのものでした。
講演では実体験をもとにした、多くの提言をいただきました。その中には「人が通る場所に転倒するものは置かない。どうしても置かなければならない場合には転倒防止対策を施す」といった当たり前ではあるが、ともすれば疎かになりがちな日常的な備えについて、経験したからこその提言がありました。また、職員の中には、こどもの避難先(小学校)で救援活動を行った方や、ご家族の安否確認のために職場にすぐに来られない方もいました。そのような状況では「(職場に)来られなかった職員を責めない」ということも非常に重要な対応であることを学びました。また、好ましくない言葉かけとして、自宅が流されてしまった方に対して「あなたは、家は流されたけど、命があってよかった」や、ご家族を亡くされた方に「遺体が見つかってよかった」などを挙げていました。被災者の方に命があってよかった(不幸中の幸い)と考えがちですが、決してそのような簡単なものではないということを痛感しました。自らも被災された八木橋先生の言葉は、参加者の心に深く刻まれました。

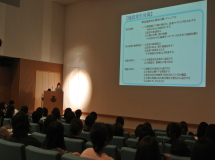
総合周産期母子医療センター
関田 真由美 澤 亜紀子
![]()
![]()


