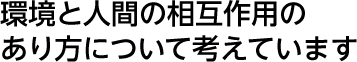国際医療協力は、先進国の優れた医療技術と医学知識を駆使して、途上国で疾病に苦しむ人々を助けたり、疾病を予防したりすることだと考える人が多いと思います。実際に多くの医学・医療の専門家が様々な国や地域で大きな成果を挙げています。しかし、疾病の治療と予防だけではなく、健康状態をより良くすることも重要な課題です。そのためには、健康とはどのようなことなのかをもう一度きちんと把握する必要があります。つまり、「疾病でなければ健康」という固定観念ではなく、健康には様々な状態があって、日々変化しており、その変化の一つの形が疾病であるという、保健学(健康科学)の視点が必要となるのです。
日々の暮らしの中で変化する健康を扱うためには日常生活の場、すなわち、環境を取り扱うことが極めて重要となります。保健学(健康科学)においてこの分野を受け持ち、環境への適応(Adaptation)について様々な分析を試みるのが人類生態学(Human Ecology)で、私の専門です。最近は、エコロジーとエコノミーの区別がつかなくなる傾向にありますが、エコロジー(生態学)とは生物と環境との関係を把握しようとする学問です。私たちが環境を変えると環境から私たちが受ける影響も変化します。人間と環境は互いに影響しあいながら常に変化していて、これを環境と人間の相互作用と呼びます。世界各地の様々な環境要因(自然環境と社会・文化環境の両方)に、人々がどのように適応しているのかを調べ、環境と人間との相互作用が健康の方向へ動いているのか疾病の方向へ動いているのかを見極めたいと考えています。具体的な研究内容は業績一覧を参照ください。
大学院の研究生活で重要なのは、決して一つの見方に偏らないことです。皆さんが将来どのような仕事に就こうとしているのかわかりませんが、どのような立場にあっても自分のやりたい仕事を続けるには柔軟な物の見方が必要なのです。大学の研究室で先生や先輩の仕事を手伝ったり、就職して上司の仕事を手伝ったりしたとき、こき使われたと思い込む若い人が多いのですが、実は、こき使われた経験は、今度自分が責任を持って仕事をしなければいけないときに必ず役立つのです。私自身、様々な局面で初めての仕事をしなければならないときに、「何とかなるさ」と構えていられるのは、大学院の学生だった頃に充分こき使ってもらったおかげだと思っています。状況の変化に臨機応変に対応できる力や柔軟な思考力が自然と身につくことが重要なのです(厚かましくなることではない)。社会ではこうした能力は強く求められていて就職の際には大きな武器にできるでしょう。若いときの苦労は買ってでもせよと昔からいいます。私も若い頃、充分苦労しました。順送りですから、年をとったときの苦労は売ってでもするつもりはありません。皆さん、私と一緒に研究を楽しみましょう。