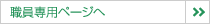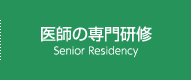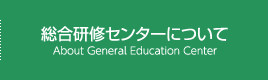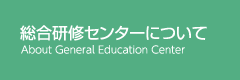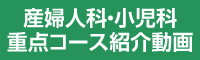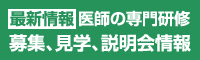職員紹介
医療職
萬 知子[センター長]
私は、2003年に麻酔科講師として杏林大学医学部付属病院に着任し、麻酔科診療・研究・教育に携わり、2010年より麻酔科学教授を務めております。杏林大学では着任後まもなく、初期臨床研修医指導医WSを受講し、そこで、赤木美智男先生(初代研修センター長)、冨田泰彦先生(現 副センター長)のご指導に深く感銘を受け、医学教育への興味が深まりました。その後は杏林大学病院の指導医WSのタスクフォースのレギュラー参加に加えて、全国自治体病院指導医WSタスクフォースも務めさせていただき、また、富士研WS受講やプログラム責任者養成講習受講など、本職の麻酔科専門医の業務とともに医学教育に関わってきました。研修センターでは病院全体の職員研修としての任務の1つとして看護師特定行為研修委員会の活動も担っております。多職種連携、働き方改革への対応など、病院として時代に沿う研修にフットワークよく取り組んでおります。
冨田 泰彦[卒後教育委員会委員長・副センター長]
1987~2007年まで本学の脳神経外科、救急医学(高度救命救急センター)にて診療・研究・教育に携わり、学位(医学博士)、日本脳神経外科学会専門医、日本救急医学会専門医を取得。特に救急医学では医学部卒前教育や初期臨床研修に深く関わった経緯から2007年4月より医学教育学専任(現在、臨床教授・副センター長)となりました。
医学部の卒前教育、卒後臨床研修教育、病院職員教育、看護学科大学院などの領域で教育推進業務を担当しています。『人のため、道のため、国のため』、『後輩や子供たちへの最高の贈り物は「教育」である』等の思いを込めて医学教育に関わっています。
田中 良太[副センター長]
皆さん、こんにちは。呼吸器・甲状腺外科学の田中良太と申します。2023年4月より医学教育学と兼務することになり、総合研修センターの副センター長となりました。私は2013年4月から2年間、シカゴ大学エバンストン病院のシミュレーションラボで働いた経験を持ちます。そして日本の外科教育の現状を知り、多くの課題や問題点に気付かされました。現在は積極的に本学における医学生や初期研修医、そして専攻医の外科研修の整備に取り組んでいます。初期研修医に対しては、2024年度より総合研修センターのCSLにおいて、毎週火曜日朝8時40分~9時40分の1時間、結紮や縫合などのカリキュラムを開始しました。外科必修のローテーションの際には、すべての研修医がここでトレーニングします。外科研修に関して何かご要望がありましたらお気軽にお声がけください。
関口 進一郎[学内講師]
2019年4月、私は杏林大学医学部医学教育学教室に着任いたしました。前任地においては、一般小児科医として、20年にわたり外来診療を担当するとともに、外来という臨床の場を活用しながら、学生や若手医師の教育に携わってまいりました。
私が初めて医学教育学的な視点に触れたのは、2001年に指導医養成ワークショップを受講したときのことでした。当時の私にはその内容が極めて難解に思われ、十分に理解するには至りませんでした。しかしながら、外来診療の場においていかに効果的な教育を行うかを模索していたこともあり、医学教育についての理解を深め、可能であれば日常の外来教育の実践に活かしたいとの思いを抱くようになりました。その思いを具体的な形にするべく、2003年から指導医養成ワークショップの運営に携わる機会を得ました。2009年からは、日本小児科学会主催の指導医講習会の世話人を務め、全国の小児科専門研修施設において指導的立場にある医師とともに、研修指導の在り方について学びを深める機会に恵まれました。
医学教育に関しては、依然として学修の途上にありますが、これまで培ってきた知識と経験を基盤とし、更なる研鑽を積み重ねながら、教育の現場で実践へと昇華させていく所存です。杏林大学においては、医学部および病院全体で、教員のみならず多職種の方々が協力し合い、学生や研修医を一人前の医師へと育て上げる文化が根付いていることを強く実感しております。私もまた、この環境の中で、杏林大学の医学教育をさらに充実・発展させるべく、尽力したいと考えております。
林 啓子[看護部副部長]
病院職員が医療人として生涯学習に取り組み、キャリア形成をしていくことができるような支援をしていきたいと考えております。総合研修センター運営会議メンバーとして、看護部門のキャリア発達支援に関する業務を主に担当しています。現在、センターと連携して実施していることとして、BLS訓練、静脈注射ライセンス取得、CVC挿入中患者の看護に関する研修等があり、適切な知識と技術で、安心・安全な医療・看護を提供していくことができるよう、教育体制を整えています。
働き方改革に伴い、タスクシフト・シェアを最大限推進していくことが求められています。事前に取り決めたプロトコールに基づいて、薬剤投与や採血・検査の実施ができるような体制整備と支援、特定行為を実践できる看護師の養成、看護補助者の教育と活用といった活動に取り組み、患者さんの多様なニーズに対し、タイムリーに対応できる人材の育成を推進しています。
病院の理念・基本方針をもとに、多職種で協働しながら地域医療および社会に貢献していく人材育成に努めてまいります。