- 杏林大学トップ
- KYORIN VOICE
- いとちプロジェクトを経て感じたこと

三鷹からいわきへ
今回私は、養生会かしま病院主催で福島県いわき市鹿島町で行われる、医療(い)と地域(ち)をつなぐ未来を考える「いとちプロジェクト」に参加しました。私たち医学生4人と看護学生4人の計8人で2泊3日を過ごしながら、医療と地域について学び合う貴重な時間でした。参加を決めた理由は、東日本大震災の被災地としての現状、そして地方都市で提供されている医療の実態を知るためでした。14年前、あれだけ大きな困難に直面 した被災地について何も知らない自分自身を恥ずかしく思うと同時に、そこで展開されている医療を実際にこの目で見るべきだと思ったからです。

いとちでの気づき
プロジェクトでは、かしま病院や、グループホームの施設に関する理解、またそこを利用する方との対話、かつて主要な産業であった炭鉱業の歴史を伝える資料館や、労災病院、さらに復興が進みつつもその悲劇を忘れないためのオブジェ、街並み等を見学しました。これらを通じて、今回一番重要だと感じたことは「人の背景の理解」でした。人は十人十色であり、一つの型に当てはまることはありません。例えば、宗教、死生観、価値観、その人を取り巻く家族、ライフスタイルなども個人で異なります。そんな患者さん方を診るには、その方の背景を理解し、受け入れることが不可欠です。これによって初めて、円滑な診察や多様な治療方法の提示が可能となるし、その患者さんにマッチした全人的医療の提供に近づけるのです。病気との向き合い方も千差万別な現代では、そうした考え方がより一層求められていると感じました。東京慈恵会医科大学の創設者 高木兼寛先生の「病気を診ずして病人を診よ」という言葉は、今回学んだことの真髄をついていると思いました。

看護学生との活動を経て
病院での活動や地域の方々を交えた、いとちワークで看護学生と活動することで印象に残った点が2つあります。1つ目は、より患者さん目線で物事を考えている点です。看護学生は、既に臨床の現場で複数の患者さんに接しているため、患者さんに寄り添い、細かな点にも気付くことができていました。2つ目 は、連携が取れていたことです。考えたことをグループにすぐフィードバックして、チームとして行動し、より良い考えに昇華させていました。看護学生とともに活動したことで、多職種連携の大切さに気付かされました。

”聞く力”の大切さ
様々な医療従事者の方々や地域の人々から話を聞く中で、自 身に足りなかったものを知ることができました。それは、「恐れずに聞く力」です。現在も、そして外国人の増加により多様化が進むことが予想される未来においても、人の背景を推測するだけではなくて理解することが必要です。これは病気の診断にこそ不可欠だと思いました。聞くことをためらって自分が受動的になって情報提供を待っているだけでは何もスタートしません。これからは能動的に話を聞いて、病気や周囲のもので人をカテゴライズするのではなく「その人はどういう人なのか」を知ることが必要だと感じました。今後は聞く力の修養に努めたいと思います。
自身の課題や、医療と地域のつながりについてもっと考えたい方は、ぜひ「いとちプロジェクト」に参加してみてください。
※記事および各人の所属等は取材当時のものです
ピックアップ

フランスと中国の手術室で過ごした2カ月
医学部医学科6年
青山 稔さん
2024年度海外クリニカルクラークシップ(フランス・クレルモン=フェラン大学ガブリエルモンピエ病院、中国・北京大学人民医院)
(2024年9月取材)




![学納金サイト [在学生・保護者専用]](/assets/images/BlkFeatured_item_tuition.jpg)


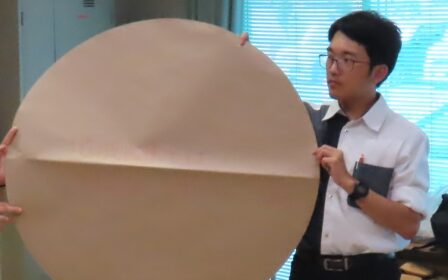


 前のVOICE
前のVOICE