世界規格となる
不整脈治療を目指して
潜在的な患者数を含めると日本人の90%にあると言われる不整脈。脈が遅くなる「徐脈」、速くなる「頻脈」の2種類のうち、頻脈の中でも、突然死の危険性があるのが「心室頻拍」です。
副島教授は、不整脈治療が進むアメリカのハーバード大学等で約8年間にわたって、心室頻拍のカテーテルアブレーション治療の研鑽を積み、マイアミ大学では不整脈センターを立ち上げました。また、新開発の心外膜アブレーション治療を日本で初めて成功させたり、欧米の医療機関などとリードレスペースメーカーを開発したりと、不整脈治療の世界を牽引し続ける副島京子先生をご紹介します。

副島 京子
(そえじま きょうこ)
1989年 慶應義塾大学医学部 卒業
1998年 米国ハーバード大学医学部 ブリガム アンド ウイメンズホスピタル 循環器科電気生理学 フェローシップ
2001年 ハーバード大学医学部循環器科 講師
2003年 同大 助教授
2008年 米国マイアミ大学循環器科 准教授などを経て
2011年 杏林大学医学部付属病院循環器内科着任
2015年 同大 教授
不整脈治療の可能性に魅了され
副島教授が不整脈治療の道を選んだきっかけは、研修医時代に出会った一人の患者さんでした。度々激しい発作を起こし、救急車で運ばれることのあったその患者さんに対して、副島教授は心電図で症状の発生経路を推定し、カテーテルで部位を確定し、アブレーション治療(心筋照灼術)を行ったところ、目の前で心電図が正常に戻り、症状が劇的に改善しました。 苦しみから解放された患者さんの顔を見て、「この道だ!」と不整脈治療を極めることを決意したと言います。
不整脈治療の先進国へ飛び込んで
国内で9年間経験を積んだ後、「より不整脈治療のスキルを高めたい」とアメリカに渡り、最新の不整脈治療を行うハーバード大学ブリガム アンド ウイメンズホスピタルで臨床医になりました。年間500例以上のアブレーション治療に携わることで高いスキルを身につけ、また、研究分野でも評価されたことで、2003年には、ハーバード大学医学部循環器科で助教授(現 准教授)に昇進し、さらに臨床医として、指導者としての経験を深めていきました。
突然死の危険がある心室頻脈 治療への新たな決意
アメリカで経験を積む中で、副島教授はある出来事をきっかけに、不整脈の中でも心室頻脈の治療に特に力を入れるようになったといいます。心室頻脈は、心室筋が異常興奮をきたしたり、心室内にできた異常回路を電気興奮が旋回することで、頻脈・動悸症状が発生し、脳血流が低下し、失神や突然死をきたす可能性がある疾患です。
主な治療法は、植え込み型除細動器(ICD)を心臓内に入れることで、発作時に電気ショックを起こし、心臓の動きを正常に戻します。しかし、その電気ショックは、雷が身体に落ちるほどの衝撃と例えられるすさまじいものです。心臓移植によって、ICDが不要になったある患者が、取り出されたICDをライフル銃で打ち抜きました。「これでもう苦痛から開放される」と安堵した姿を目にした時に、「ICDが作動する前の段階で病状をコントロールできる治療を行いたい」と、アブレーション治療を研鑽するようになりました。
日本で初めて成功させた新治療法
アメリカでの経験は、「世界各地から優秀な医師が集まる環境の中で、常に新しい知識や技術を学ぶことができた」と話す副島教授にとって、大きな出会いの一つが、「心外膜アブレーション」治療を開発したブラジルのソーサ博士でした。
症状が心外膜付近にある場合、心内膜側からアプローチをする従来のアブレーション治療では、患部に届かず限界がありました。しかし、ソーサ博士はそれまで難しいとされてきた心外膜側からのアプローチ法を編み出しました。副島先生はその画期的な手技を学ぶためブラジルに渡ると、1週間で取得。その後は、ハーバード大学でこの手技を広め、2004年には日本で初めて心外膜アブレーションを成功させ、国内でこの治療法が広がる礎を築きました。
杏林大学から世界規格となる治療を発信
2011年に杏林大学に着任すると、これまでの経験とマイアミ大学で一から不整脈センターを立ち上げた経験を生かし、不整脈センターを作りました。 専門性の高い医師や看護師などでチームを作り、患者の治療から日常生活までを総合的にサポートしています。

常に技術革新を求めて
2014年には、欧米の医療機関と共に世界最小のリードレスペースメーカーの開発に協力しました。徐脈性不整脈の治療として心臓に埋め込まれるペースメーカーは、リードの断線による故障やリードによる感染症の発生など複数のリスクがあります。
こうした不安要素を取り除き、身体への負荷を最小限にした長さ約2.6cmという最小のリードレスペースメーカーは、2017年に誕生し、日本での1台目は当院に導入されました。現在、世界各地の不整脈治療に取り入れられています。
また現在は、不整脈の早期発見をめざして、ウエアラブル装置の開発に企業と取り組んでいます。「自覚が難しい不整脈の症状になるべく早期に気づき、病院を受診することで、脳梗塞など病気の予防・治療につなげたい」との考えから、腕時計型脈波計で得られる脈波データから脈の乱れを検出する装置の研究開発を行っています。


後進への支援
若手医師の支援のひとつとして副島教授は、日本不整脈心電学会で女性医師を支援するプログラムに携わっています。まだまだ女性は男性と比較して、ライフイベントのために仕事が中断することへの不安や家庭との両立が困難といった悩みを抱えています。そのため、学会で勉強や情報交換会を行うことで医師達が切磋琢磨できる機会を提供しています。 また、学内では女医復職支援委員会で、復職支援制度の活用をサポートするなど、女性の医師達の環境を整える取組みも行っています。
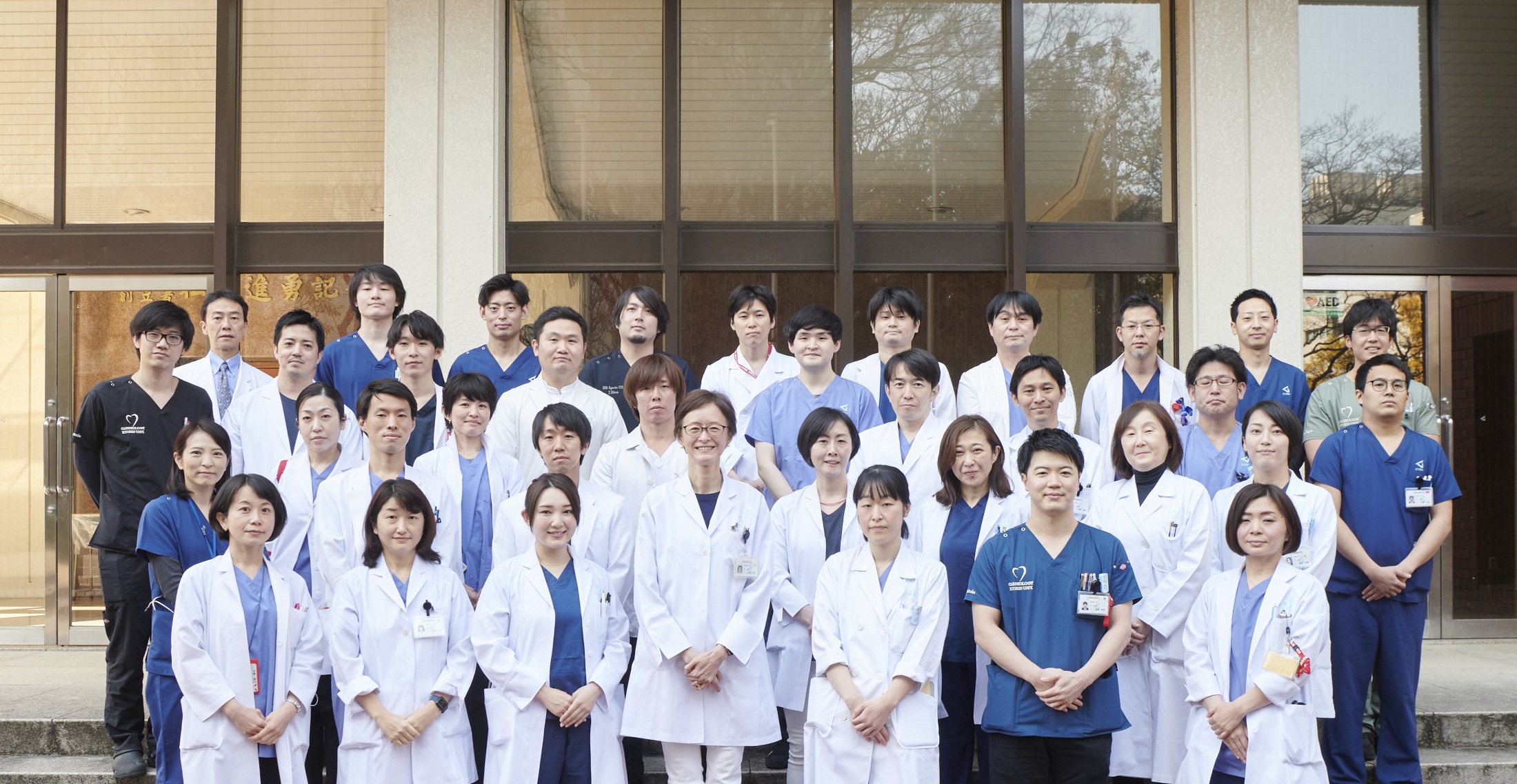
学生へのメッセージ
積極的に世界を広げ 切磋琢磨を
医師として成長するためには、様々な経験や出会いを通して、自分の視野を広げることが大切です。私は30代で渡米し、これまでと全く異なる環境に身を置き、世界各地の優秀な医師達と切磋琢磨したことで、スキルの向上に加え、要所要所で道を拓く手がかりを得ることができました。学生の皆さんもどんどん外に出て、刺激を受けてください。恥ずかしがらず他領域の人たちとも出会い、広い知識や経験を積んでください。
循環器は緊急が多くて体力に自信がある人しか無理、と思わず是非見学に来てください。心電図やエコーなど女性にも取り組みやすく、今後急速なデジタル化が進歩する領域が循環器です。
デジタル化により“働き方改革”も期待されます。アプリを使った患者診断や治療など今後さまざまな研究を続けていきたいと思っています。是非お声がけください
2022.6掲載当時




![学納金サイト [在学生・保護者専用]](/assets/images/BlkFeatured_item_tuition.jpg)
